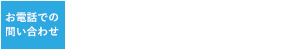左官工事の基礎知識!使われる材料とその特徴
2022/09/30
左官工事は、日本の伝統的な仕上げ段階の工事で、かつては建築に欠かすことのできない工程のひとつでした。高度経済成長以後、新建材の開発、普及によって衰退しましたが、近年、環境志向やシックハウス症候群対策、自然素材の再評価など健康志向により見直されています。
しかし、あまり馴染みのない人も多いのではないでしょうか。左官工事とはどのようなものか、使われる材料、特徴などについて解説していきます。
左官工事の基礎知識

左官工事とは、土、水、砂、草、繊維などを混合した材料で建築物の下地や内外装を仕上げる工事です。職人がコテを使って塗り仕上げる手作業であり、繊細で高度な技術、豊富な知識と経験が必要です。歴史的には少なくとも1000年前から使われています。
日本は四季があり雨が多いため湿気の変動が大きい気象条件であることから、建築物に湿気の調節のため土壁と漆喰を取り入れました。また、日本は地震が多い国でもあります。地震の揺れで土壁と漆喰が割れたり崩れたりすることでクッションのような役目を果たすことで揺れを軽減することができます。
現在でも主に寺社建築や城郭建築では全面的に左官工事が続いています。上に述べた機能面だけでなく、姫路城などに代表される意匠面でも知られています。
仕上げる工事がメインとはいえ、実際には下地つくりや下塗りなど仕上げるための予備工程が多くを占めています。
主な材料と特徴

土壁
主に和室で使われます。土の調合によって表面の質感や色合いに変化があります。日本の気象に合っていて、機能面では調湿性の他、消臭効果、防火性も高い材料です。
しかし一時はほとんど使われなくなったため技術が途絶えかけていて、熟練した職人がいなくなったため、施工には時間と費用がかかります。
モルタル
砂と水とセメントを混合したもので、グレーっぽい色合いになります。比較的シンプルな作業で、費用も抑えられるため広く使われています。
表面が硬く仕上がり、耐久性も高いため外部の床など水平部に使われることが多く、基礎工事の仕上げやタイル工事の下地にも用いられています。
漆喰
石灰に海藻や砂や糊などを混合したものです。ホコリやゴミなどが付きにくく、湿度の高い時期は水分を吸収し、逆に乾燥する時期は水分を放出して調湿します。原料が不燃性で防火性が高いことから、防炎、防火効果が認められています。また、アトピー性皮膚炎やシックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドを吸着・分解することから、健康志向のニーズに応えられるとして再評価され、一般住宅でも採用が増えはじめています。湿気が気になる部屋や和室、トイレには漆喰が向いています。
色調はホワイトで、瓦屋根の面戸やつなぎにも使われています。
珪藻土
海や湖の藻類が化石化し、底に堆積したものです。除湿機能が高く、最近よくバスマットに用いられたことがきっかけで広がりました。自然素材で有害な化学物質を含まないため、アトピー性皮膚炎やシックハウス症候群などのアレルギー症状を引き起こす心配がありません。その他にも吸水性、消臭効果、耐火性、断熱性が高いです。臭いが気になる玄関やトイレには珪藻土が向いています。
ジョリパット
主にアクリル樹脂が使われます。デザイン性が高く、施工性もいいため比較的安価で人気があります。外壁でも内装でも幅広く使われ、ホテルや商業施設などでも多く使用されています。耐用年数が長く、ひび割れもしにくい反面、凹凸があるデザインのためホコリなどの汚れが溝の部分に溜まりやすくなります。
まとめ

左官工事の基礎知識、使われる材料とその特徴について解説してきました。左官工事は、全般的に人間の身体にとって良い素材が使用されています。しかし、その施工には職人の確かな技術や長く豊かな経験が不可欠で、システム化や大量生産には向いていません。そのため工期も長くかかり、費用も高めになります。特に漆喰などの特殊な技術と経験が求められる左官では、施工できる職人がかなり限られてきています。
-
前の記事
記事がありません
-
次の記事

漆喰の役割と特徴について 2022.09.30