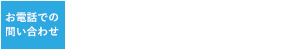左官工事で使われる材料とは?その種類と特徴について解説
2022/12/30
左官工事でどんな材料が使われるかご存じですか。
この記事では、材料の種類と特徴について解説しますので、左官工事を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
左官工事とは

そもそも左官工事とはどんな工事でしょうか。
左官工事とは、コテを使って壁土やモルタル、しっくいなどの材料を建物の床や壁を塗って仕上げる工事です。住宅だけでなく寺院やお城など伝統的な建物にも採用されています。
伝統的な技術で、継ぎ目なく塗り上げられた美しい仕上げができるのが特徴です。
また、タイル仕上げの下地をつくるときにも左官工事が行われます。モルタルを使って平滑な下地をつくり、タイルをきれいに仕上げられるようにします。
左官工事に使われる材料と特徴

左官工事に使われる主な材料は、しっくいや珪藻土、モルタル、土などです。
水や空気と反応することで固まって仕上がります。
左官工事では、材料が固まらないうちにコテを使って床や壁に材料を塗ることになります。
主な材料の特徴について解説します。
漆喰
漆喰は左官工事で使われる代表的な材料です。
消石灰やすさ、海藻のりを混ぜ合わせてつくられた材料で、古くからお城や壁の仕上げに使われています。
白く滑らかに仕上がる美しさに加えて、燃え広がりにくい特徴を持っているので防火対策の材料として使われています。今ではシックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドを分解する働きがあり、消臭効果もあるので、住み心地のよい空間を実現できる仕上げ材として見直されています。
珪藻土
珪藻土も左官工事でよく使われる材料です。
植物プランクトンの一種である珪藻の殻が、海底や川底に堆積し固まった土を原料にしてできたのが珪藻土です。日本は、海に囲まれ河川にも恵まれているので、珪藻土が豊富に採れます。
珪藻土の一番の特徴は除湿効果の高さです。珪藻土の粒には、細かい穴が無数に開いているため空気中の水分やにおい成分を吸着しやすいためです。
近年、除湿効果の高さから室内の仕上げ材として人気があります。また、建物自体が水分を含みにくくなるので柱や梁などの構造部が腐ることなく、長持ちさせることができます。
モルタル
モルタルは、仕上げと下地をつくる目的のどちらにも使われる左官の材料です。
セメントと砂、水を混ぜ合わせてつくられた材料で、耐久性の高さを活かして床の仕上げに使われることがあります。
仕上がった色がグレーになるので、モダンな雰囲気、インダストリアルな雰囲気の空間づくりを目的とした仕上げ材料として使われることもあります。
聚楽壁
一般的な和室の仕上げ材に使われているのが、聚楽壁といわれる土からできた材料です。
安土桃山時代に豊臣秀吉が京都に建築した聚楽第の跡地付近の土が利用されたことから、その名がついたといわれる材料です。京壁と呼ぶこともあります。
ざらっとした茶褐色の仕上がりになり、混ぜ合わせる土によっては、その色味が変わります。茶室や和室の壁の仕上げ材として使われ、耐火性が高い特徴があります。
モールテックスとは?
リノベーションを検討している方に人気のある材料にモールテックスがあります。
海外製のコンクリート調の仕上げを再現できるので、近年流行のインテリアデザインに合った材料です。
モルタルと同じような原料に加えて特殊な樹脂を混ぜ合わせた材料で、水を通さない特徴があるので、浴室や洗面ボール、キッチンのシンクの仕上げ材としても活用できます。
左官の材料としては、下地材を選ばず、非常に薄い塗り厚で仕上げることができ、固まった後は耐久性にも優れている特徴があります。表面の強度はコンクリートの5倍ともいわれます。
一般的な左官材料と比較して仕上げるまでの工程が余計にかかるため、工事費用は少し割高となります。